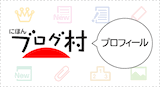今回は稲庭うどんについて書いていこうと思います
答えは秋田県湯沢市稲庭町が発祥です
また秋田県はたはたやきりたんぽも有名ですよね
秋田名物「なまはげ祭り」や「秋田竿燈祭り」も観光で有名です
稲庭うどんは秋田県湯沢市稲庭町が発祥
稲庭うどんは、秋田県湯沢市稲庭町発祥の手延べ干しうどんで、日本三大うどんの一つとして知られています。滑らかな喉ごしと独特のコシ、上品な味わいが特徴で、伝統的な製法を守る名店や製麺所が数多く存在します
日本三大うどんとは
日本三大うどんとは、日本各地のうどんの中でも特に有名で歴史や個性を持つ三つのうどんを指す呼称です。ただし「三大うどん」には明確な定義がなく、地域やメディアによって候補が異なる場合があります。
主な三大うどんの構成
多くの場合、以下の2つは必ず挙げられます。
- 讃岐うどん(香川県)
- 稲庭うどん(秋田県)
三つ目については、主に以下の2つが有力です。
- 水沢うどん(群馬県)
- 五島うどん(長崎県)
このため、「三大うどん」は以下の2パターンが一般的です。
| 讃岐うどん | 稲庭うどん | 水沢うどん or 五島うどん |
|---|---|---|
| 香川県 | 秋田県 | 群馬県または長崎県 |
また、富山県の「氷見うどん」を加えて「日本五大うどん」と呼ばれることもあります。
それぞれの特徴
- 讃岐うどん(香川)
太めでコシが強く、もちもちした食感が特徴。全国的な知名度を誇る。 - 稲庭うどん(秋田)
手延べ製法による細く滑らかな麺で、つるりとした喉ごしが魅力。 - 水沢うどん(群馬)
透明感のあるツヤとつるつるした喉ごし、しっかりしたコシが特徴。ごまだれで食べるのが伝統的。 - 五島うどん(長崎)
細麺ながら強いコシがあり、椿油を使った手延べ製法が特徴。アゴだし(トビウオだし)で食べるのが定番。
日本三大うどんの特徴
日本三大うどんとしてよく挙げられる「讃岐うどん(香川県)」「稲庭うどん(秋田県)」「五島うどん(長崎県)」または「水沢うどん(群馬県)」の特徴を詳しく解説します。
讃岐うどん(香川県)
- 特徴
太めで四角い断面、非常にコシが強く、もちもちとした食感が特徴です。
つるつるとした喉ごしで、弾力のある麺が楽しめます。 - 製法
足踏み製法で生地をしっかり練り上げることで、独特のコシを生み出します。 - 食べ方
かけうどん、ぶっかけ、ざるうどん、釜玉うどんなど多彩な食べ方があり、セルフサービスの店も多いです。
稲庭うどん(秋田県)
- 特徴
手延べ製法による細く平たい麺で、なめらかな舌触りとつるりとした喉ごしが魅力です。
麺自体がやや半透明で、上品な見た目も特徴です。 - 製法
小麦粉と塩、水だけで作られ、手作業で延ばして乾燥させる伝統的な製法です。 - 食べ方
冷やしてざるうどんとして食べるのが一般的ですが、温かいメニューにも使われます。
五島うどん(長崎県)
- 特徴
手延べ製法で作られる細麺ながら、強いコシとぷるんとした食感が特徴です。
椿油を生地に塗りながら延ばすため、艶やかな見た目となめらかな口当たりが生まれます。 - 製法
生地を棒状にして箸にかけて引き延ばし、椿油を塗布して仕上げる独特の工程です。 - 食べ方
あごだし(トビウオだし)で食べる「地獄炊き」など、独自の食文化があります。
水沢うどん(群馬県)
- 特徴
四角くやや太い麺で、透明感があり、つるつるとした喉ごしとしっかりしたコシが特徴です。 - 製法
良質な小麦粉と水沢の名水を使い、手打ちで作られます。 - 食べ方
ごまだれや醤油だれで食べるのが伝統的です。
| 名称 | 産地 | 製法 | 太さ・形状 | 主な特徴 | 主な食べ方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 讃岐うどん | 香川県 | 手打ち | 太め・四角 | 強いコシ、もちもち感 | かけ、ぶっかけ等 |
| 稲庭うどん | 秋田県 | 手延べ | 細め・平たい | なめらか、つるつるの喉ごし | ざる、温かい汁等 |
| 五島うどん | 長崎県 | 手延べ | 細め・丸い | 椿油使用、強いコシ、艶やか | 地獄炊き、あごだし等 |
| 水沢うどん | 群馬県 | 手打ち | やや太め・四角 | 透明感、つるつる、しっかりコシ | ごまだれ等 |
それぞれのうどんは、地域の風土や文化、製法の違いによって個性豊かな味わいと食感を持っています。
まとめ
今回は日本三大うどんの一つ「稲庭うどん」に書きました書きましたが
皆さんはどこのうどんが気に入ったでうす?