節分は、厳密には各季節の始まりの前日を指しますが、現在は主に立春(春の始まり)の前日を指します。通常は2月3日と思われがちですが、実際には立春の日によって2月2日や4日になることもあります
節分の由来
立春は、節目のうえでは冬から春へと季節が変わる日となります。古来より、季節の変わり目にはいつもと違うことが起こったり、予期せぬ出来事に見舞われたりしやすいとされてきました。
そこで、立春となる前日に悪いものを追い払い、幸運が舞い込むようにと願って節分の行事がおこなわれるようになっていきました。節分のはじまりは平安時代や室町時代など諸説ありますが、日本に古くからある伝統的な行事の1つとなっています。
歴史と意味
- 旧暦では、春が新年の始まりとされていた
- 季節の変わり目に邪気を払い、幸運を呼び込む目的で行われる
- 「鬼は外、福は内」という言葉とともに豆まきを行う。
豆まきの目的
豆まきは、病気や不幸といった「鬼」を追い払い、福を呼び込むための伝統的な儀式です。現代では、心の中の悪い感情を追い払う意味も込められています。
節分の食べ物
恵方巻
節分に食べられる太巻き寿司「恵方巻」は、関西を中心に食べられていましたが、今では全国に定着しつつあります。「縁を切る」に通じないよう、一本巻きに巻いた恵方巻を、その年の恵方(縁起が良いとされる方角)を向き、無言で1本食べきるのが正しい作法とされています。無言で食べるのは「話すと運が逃げていく」と考えられていたことに由来するようです。
こんにゃく
こんにゃくは「体の中を綺麗にする食べ物」として、1年の節目に食べる風習を持つ地域もあります。節分にもこんにゃくを食べ、体の中にある悪いものを出す目的で食べられます。
イワシ
焼くと強い匂いのするイワシは、焼いて食べた後の頭を柊の葉に刺し、玄関へ飾ると鬼が嫌がって入ってこないと信じられていました。
都会やマンションなどでは見かけることも少なくなりましたが、頭は飾らなくてもイワシのフライやオイルサーディンなどを食べる場合もあるようです。
そば
「年越しそば」は、新年を迎える前の日に食べられていますが、もともと「旧暦の立春前日」、つまり節分の日が大晦日だったため、現在でも節分にそばを食べることがあります。
けんちん汁
神奈川県鎌倉市にある建長寺のお坊さんが作っていたのがはじまりだとされるけんちん汁。縁起の良い食べ物として、節分にけんちん汁を食べる地域もあります。
くじら
大きな生き物の肉を食べるのも縁起の良いこととして、山陰地方などでは節分にくじらが食べられる風習があるようです。
まとめ
2025年は2月2日が節分になります。そして今回の恵方巻の方角は「西南西」です
なるべく無口で食べるといいそうです。豆はよく年の数と言われますが
私は食べれません(笑)
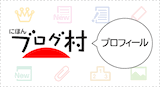
人気ブログランキング


